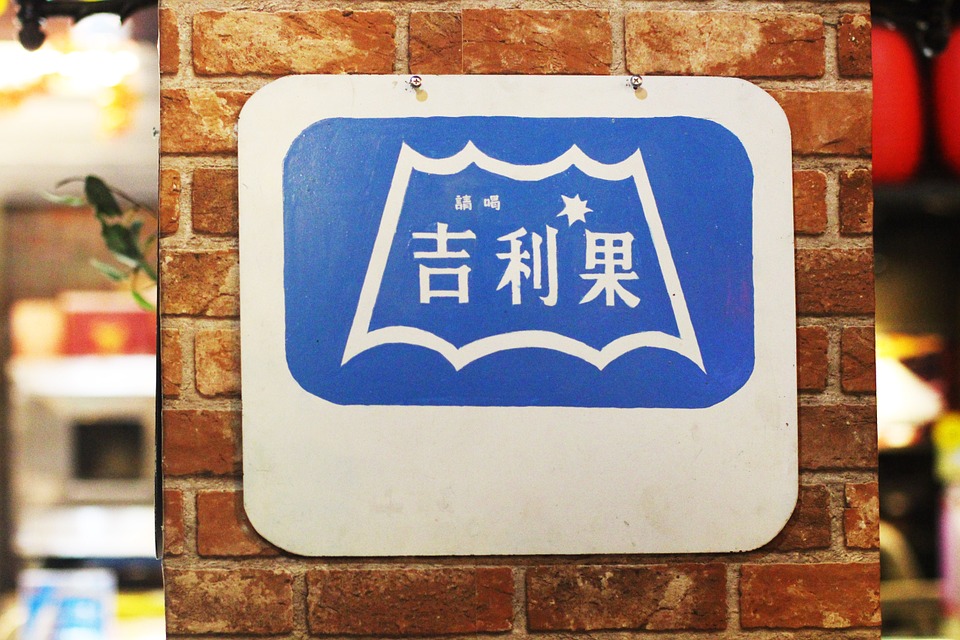――「民國の衰亡、蓋し謂あるなり」――渡邊(2)
渡邊巳之次郎『老大國の山河 (余と朝鮮及支那)』(金尾文淵堂 大正10年)
世界的に認められた「民族自決主義に一致せる日韓併合」によって、朝鮮半島には「平和と安寧と幸福と文化」とがもたらされた。つまり「擾亂、強奪、誅求、壓制、窮苦、寒慘、薄瘠、其他あらゆる厭惡すべき文字を以て自然と人事の總てを形容するも足らざる惡政の下に、人心地もなく生活したる一千五百万餘萬の鮮人」を救い出し、彼らに「今日何の點においても殆ど日本と擇ばざる太平と文化と繁榮との下に、世界五大強國の民族として、樂しき生活を送りつゝあるに徴して明白なりといふべ」く、「日鮮同族の親和結合は、現代思潮の民族主義を最も完全に發揮する所以といふべきなり」である。
――このような渡邊の主張を、現代の視点から批判することは容易い。ここでは日韓併合問題について深入りすることを避けておくが、やはり当時、こういった主張が大阪毎日新聞で堂々と論じられていたという事実を確認しておくに止め、渡邊の旅を急ぎたい。
鴨緑江を渡って朝鮮を離れ、中国人が営む安東県に入った。
車中からチラッと目にしただけだが、建物は朝鮮の街と較べ「やゝ高大にして整然、復殆ど白衣の影を見ず、喧囂、殷賑、人亦活氣を有せるの趣あり」。ここから「鮮人の支人に及ばざる、一見して明らかなるを得るが如し」。
広大な満洲で目にした人々を「其純朴の風や愛すべきものをあるを思」うが、それがまた「支那の支那たる所以」だ。「徒に無懷氏の民尚多くして人文の進歩なく、晝耕夜息、帝力何か我にあらんやと嘯くも、比々皆然るの状なるを察知し得べく、彼等のため支那の爲に悲しむべきなり」と綴る。
次に渡邊は「一滿鐵職員の能く語る」ところを引用し、両民族を比較する。それによれば、「支那人は利に偏して氣慨乏しく、朝鮮人は意氣稍日本人に類するものあり、必ずしも利を以て誘ふべからず、其信念の發する所、其敵愾の迸る所、慷慨激越、斷じて非禮を受けず、昂然として威力に抵抗し、得失と休戚とを問はざるもの少なからず、時に學童亦排日の理由を説いて肯綮に當るものありといふ」とか。
奉天で渡邊は「平滑無髯の一紳士」で「言語平靜、一點矯激のところ」のない「赤塚總領事」と面談し、滿洲問題について意見を交換している。
「日本人の朝鮮に移住して鮮人を驅逐し」たことから、「鮮人の滿洲に入り込み支那との間に面倒な交渉の頻起するは面白からず」。だから「寧ろ日本人の朝鮮を飛越して滿洲に移住するを可とする意見」もある。これまで「日支葛藤の調査し來」たが、「非慨し我にあり」。「又陸軍側に徒に威武を輝かすに偏するを非とする」――こう総領事が説いた。
総領事の説いたところが当時の外務省公式見解と言うわけではないだろうが、それにしても我が外交最前線に在った奉天総領事が、「日支葛藤」に関わる「非」が「慨し我にあ」るばかりか、軍事的影響力に過度に偏る陸軍の対応を「非」としている点は注目しておきたい。
総領事の話に耳を傾けながら渡邊は、「支那政局に中心點なく、勢力相錯綜し、一斑を以て全豹を斷じ難」いから、「一切の交渉問題、交渉の徑路等」は「内房に私議して」こそ「平隱なる決着を得」ることができる。「人道と正義とを標榜せる外交」という立場に立って、「鮮人移入によつて生ずる問題」の外交的解決を目指も外務当局にとっての障害は「陸軍の武斷的態度」である。だが「外交當局の微力」「自己權限の小少」という現実を前に、打つ手なし――との“嘆き節”と受け取った。
たしかに満鉄(政府)、陸軍、外務省の3者の権限が錯綜しているだけに満州問題解決は困難ではある。だが外交交渉当事者が泣き言を口にしてどうす、と渡邊は憤る。《QED》