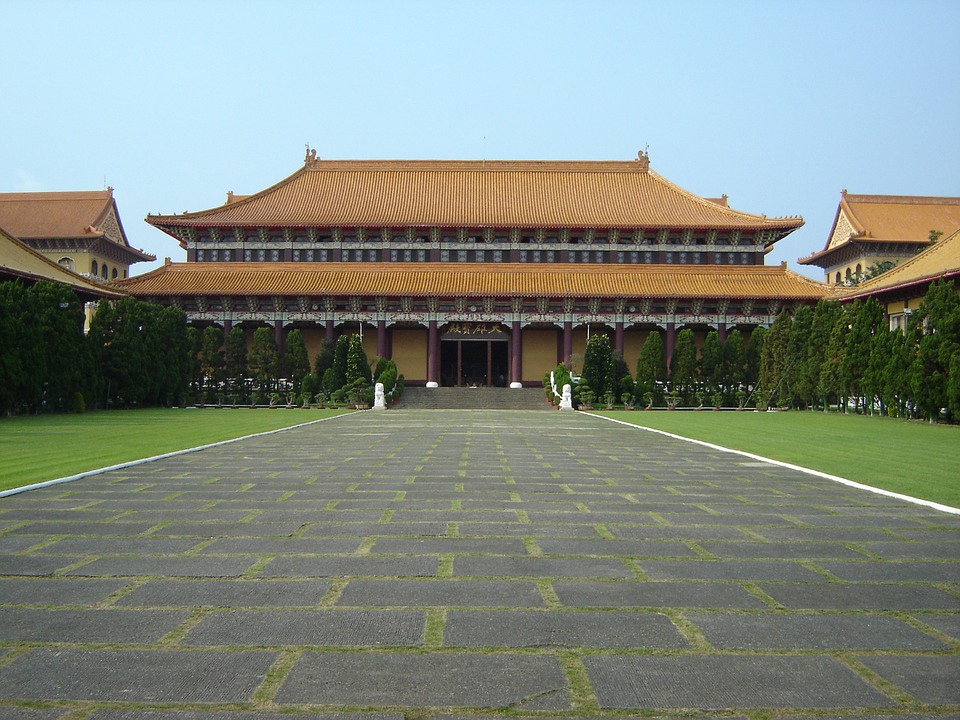――英国殖民地だった頃・・・香港での日々(香港13)
殖民地経営のためのソフトとハードの両面にわたる全機構を、ほぼそのままの形で特別行政区が踏襲したと考えるのが、おそらく「中国回帰」の実態に近いのではないか。イギリス駐留軍の総司令部と駐屯地を人民解放軍香港駐留部隊が“居抜き”で引き継いだことや、殖民地時代には宗主国イギリスの枢密院司法委員会が持っていた法律の最終解釈権を全国人民代表大会常務委員会が掌握していることなどが、その象徴と言えるだろう。
特区政府のトップに立つ行政長官にしても、総督以上の権能を持たない。いや中央政府の権限がより強化されているだけに、もはや操り人形以上の意味を望めはしない。行政局は行政会議、立法局は立法会と漢字表記が改まりはしたが、香港独自の行政や立法は不可能だ。香港基本法は「高度な自治」の意匠が施された“拘束衣”ではなかったか。
経済の中心はイギリス系資本から香港地場の巨大企業集団に代わったが、主要な企業家は例外なく親中派だった。親中派として振る舞うことが企業経営に好結果を生み、同時に“免罪符”となるわけだから、やはり掛け「利」は「理」に勝る。
こう見ればこそ、中華人民共和国特別行政区と名乗る香港の社会構造はイギリス殖民地時代と大差はない。確かに極論だとは思うが。
テレビに映るニクソン米大統領の訪中シーンを見ながら「不当なイギリス殖民地を脱し、香港は中国に戻らなければならない。だが、オレの目の黒いうちはムリだろう」と諦念を吐露してくれた左派の友人に、現在の香港について率直な感想を聞いてみたいもの。依然として左派の立場に在ったとしても、現状を好ましとは見ていないはずだ。1974年頃にアメリカ留学に旅立つ彼を見送ったが、現在でもアメリカで暮らしているだろうか。
昨年6月来の香港については、現在の若者は「深い山へと逃げ込む」ことを拒否し“新たな宗主国”に果敢に抵抗を試みる、といった程度に止めておく。
ここで話題を半世紀前の新聞報道に戻すと、日常的に、しかもリアルな形のままで死体写真を掲載していた。当時のことだからモノクロ写真だったが、紙面からは確実に“生々しい現場”が浮かび上がってきたものだ。今でも鮮明に思い出す写真が2枚。1枚が投身自殺(あるいは他殺?)で、もう1枚が木から吊るされた焼身死体である。前者は『星島日報』で、後者は『天天日報』だったと記憶している。
些か薄気味悪いことだが、残酷な現場写真が一切の規制がないままに新聞に掲載され、しかも読者から「人道上の配慮が足りない」などと言った類の抗議の声が起きなかったから不思議ではある。だが、それが当時の香港におけるメディア状況でもあった。
さて1枚目である。
新聞紙面中央に大きく掲載されているのは、道路に叩きつけられたうつ伏せの死体写真だ。足の関節は、反対方向に異様に曲がり、周囲は血の海。飛び降りた地点と思しき高い位置から写されたのだろう。じつにリアルに現場の情況を捉えている。カメラマンは警察や消防、救急隊より早く現場に駆けつけ、死体収容以前に現場の真上からシャッターを押したに違いない。否が応でも死体の様子が判るアングルで写された迫真の報道写真だ。
しかもゴ丁寧なことに、「これが死体です」と確認させようというのか、写真の死体は黒の太い線で囲まれている。高所から誤って落下した事故なのか。自殺なのか。それとも投げ捨てられた殺人なのか。
読者の目に飛び込んでくるのは、路面に打ちつけられ、手足が異様にネジ曲がった死体そのもの。現場保存などクソ喰らえ。交通事故であれ殺人事件であれ、カメラマンは現場に急行し、猛禽のように死体にとりつき、ファインダーの先に死体を捉え、シャッターを押し続け、これでもかと言わんばかりに衝撃の死体写真を読者に提供してくれる。《QED》