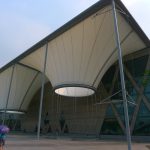――習近平少年の読書遍歴・・・“あの世代”を育てた書籍(習71)
参加者の顔ぶれからして、同会議は当時の日米両国リベラル派による佐藤政権(64~72年)とニクソン政権(69~74年)が進める対中政策に対する批判集会の様相を呈していた。
主要論題は中国政策ではあったが、会議参加者を悩ましていた大問題はドロ沼に入り込んでしまったヴェトナム戦争であったに違いない。
ここで長期泥沼化の様相を見せつつあるウクライナ戦争が招いた台湾海峡情勢を考えると、21世紀20年代の現在が、なにやら半世紀昔の中国をめぐって揺れ動くアジア情勢に重なってくるから不思議だ。
現在を新たな「ASIAN DILENMA」と捉えるなら、やはり「ASIAN DILENMA」の真の主役が中国であることに変わりはない。とは言え、中国の武器は強固なイデオロギーから対外開放を機に蓄えた旺盛な経済力へと劇的な変化を遂げたわけではあるが。
会議参加者は中国を国際社会に参加させるべきという点では一致していたものの、前提としての台湾問題の取り扱いでは違っていた。台湾独立の困難さを指摘する宇都宮に対し、ケネディ上院議員などは国連における台湾の議席を残しながら台湾独立化(⇒「2つの中国」、あるいは「一中一台」)政策を推進することが現実的だと主張している。
ここで興味深いのが、当時の日米間の懸案であった70年の日米安保改定問題と沖縄返還問題をめぐっての議論だ。参加者の1人であるライシャワー教授は「かりに日本から米軍基地がなくなったら、シーレーン防衛のために第7艦隊に代わるような兵力は最低限必要だ。だが、そのような行為は中国との間で軍事的対決状態を生み出すだろう」と、日本がアメリカの核の傘の下で日米安保を堅持することの有用性を主張している。いいかえるなら日本は“アメリカのポチ”のままでいるべきだ、ということになる。
『中国政策』を通じて基本的に感じられることは、当時のヴェトナムが現在のウクライナに代わっただけで、日米両国における「ASIAN DILENMA」の基本構造に大きな変化がみられないばかりか、一向に解決・解消される気配はないということである。その根本原因を、やはり中国に対する、殊に日本側参加者の甘い認識に求めることができようか。
「旧中国時代横行した匪賊や強盗は跡を絶ち、軍隊と官吏のわいろ着服、不正は全くなくなった」(宇都宮)とか、「中国の核兵器開発は、攻撃的な目的のものではない」(赤城)とか――当時の自民党リベラル勢力が掲げていた中国観は、呆れるばかりに無知蒙昧で無責任。その姿勢は、さながら岸田首相の「聞く力」に近いと言っておきたい。「聞く力」は「考える力」を経て最終的に「決断する力」に繋がってこそ意味を持つはずだ。
閑話休題。
『中国政策』とは肌合い異にするが、アメリカ流の国際関係論的視点から中国を論じた『世界の中の中国』(衛藤瀋吉・岡部達味 読売新聞社 昭和44年)を振り返っておくことも必要だろう。それというのも、学問的枠組みに拘る余りに限界が感じられるからだ。
当時、衛藤は水を得た魚のようにマスコミを通じて時務情勢論、さらには「無告の民」をキーワードに警世の発言を盛んに行い、岡部は『人民日報』の記事に現れる語彙などの数量的分析に基づく共産党の内外政策の変遷を論ずるなど地味な研究に精を出していたと記憶する。
『世界の中の中国』には、文革勃発直前から始まって文革で毛沢東が勝利を収め、国を挙げての大混乱が一先ず収拾しかけた1969(昭和44)年までの数年間に衛藤と岡部が発表した8本の論文を収めてある。因みに当時の中国の人口は8億前後で、国連の安保理常任理事国のポストは依然として中華民国(台湾)が押さえていた。中ソ両国の対立は緊迫の度を加え、全面軍事衝突一歩手前までエスカレートしていたのであった。《QED》