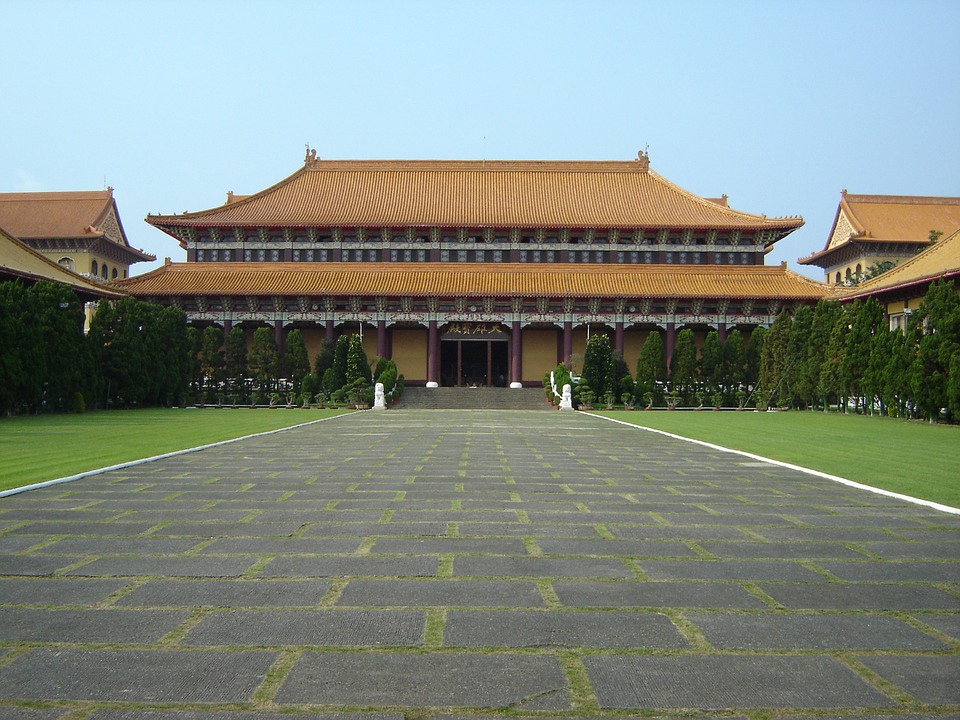――「ポケット論語をストーブに焼べて・・・」(橘77)
「國民黨の再分裂」(昭和2年/『橘樸著作集第一巻』勁草書房)
国民党左派の「首領」である汪精衛が、南京国民政府を率いる蔣介石を「(軍司令官としての)本來の任務及び職權を越えて政治に干渉し、更に進んで政權を壟斷する」「軍閥的存在」と非難することに間違いはない。だが、その汪もまた湖南や江西の軍閥に頼らざるを得ないのだから、仲間や孫文夫人からも「三下半を叩き付けられるに至つたのではないか」――こう、橘は武漢国民政府崩壊の背景を見ている。
なにやら“目クソ、鼻クソを笑う”の構図と言ってもよさそうだ。そこで思うのだが、目クソと鼻クソの双方を生んだ孫文とは、いったい、なんだったのだ。
国民党左派の重鎮として農民運動を指導した鄧演達は「農民運動は革命運動であり、農民の解放を要求するものである」と説く。鄧は自らの失敗を「農民と密接な關係を結ぶことが出來ず、從つて農民の實際要求を了解し得なかった」からであり、「我々は自ら農村の中に入込まなくてはならない」と反省する。まさにロシア革命の「フ・ナロード(民衆の中へ)」の二番煎じのような態度を、橘が「(国民党左派の)農民運動に於ける急進派の小児病的過失」と切り捨てるのは正しい。
だが「湖南・湖北は惡質なる哥老會の根強い勢力を擴げた地方であり、從つて革命的社會運動が動もすれば無頼漢の掠奪を目的とする暴動に陷り易い傾きがある」との見解を示しながら、「運動の中から無頼漢を排斥する努力を殆ど全く打忘れて居るものゝやうに見える」と鄧を批判する。また、「帝國主義者や軍閥や土豪劣紳の重なり合つた搾取を受けて落ちぶれた失業農民である。換言すれば惡勢力の犠牲となつた農民無産階級である」との「無頼漢」に対する鄧の「議論は大體正しい」としながらも、「中國の社會運動における無頼漢の危險性に對して、深い省察を缺いて居る」と苦言を呈す。
とどのつまり「運動の中から無頼漢を排斥する」ことを求めているようだが、このような橘こそ「小児病的過失」であり、同時に中国社会の根本構造についての「深い省察を缺いて居る」と言っておきたい。無頼漢は中国社会の日常の外にはみ出しているわけではなく、じつは内側に組み込まれた存在と見做すべきだろう。
はたして橘は「運動の中から無頼漢を排斥する」ことで、革命にとって有利な状況が生まれるとでも思っていたのか。革命をキレイゴトと捉えてい過ぎではないか。
毛沢東は「革命とは、客を招いてごちそうする事でもなければ文章を練ったり、絵を描いたり、刺繍をしたりすることでもない。そんなお上品でおっとりとした雅やかなものではない。革命とは暴力である。一つの階級が他の階級を打ち倒す激烈な行動なのである」と見做している。まさに一切のタブーを排し、敢えて「無頼漢の掠奪を目的とする暴動」を利用してでも目指そうというのが革命だろう。だから革命無罪を掲げるに違いない。
中国の革命史を紐解けば、革命勢力は哥老会のような会党や馬賊など無頼漢(アウトロー)との連携を模索した。たとえば湖南派の重鎮として辛亥革命を指導した宋教仁は、1904年10月末から1907年4月初までの3年半ほどの東京における活動を記した『我之歷史』(中國現代史料叢書・第一輯 建国民國/文星書店 1962年)の末尾で、概略次のように綴っている。
「明末、清朝軍が中国本土に闖入し、明朝を遥かに超えた苛烈な暴政を布いた。そこで馬賊団体が反清朝に決起し力を持ったことから、北方では彼らに身を投じ、身の安全を守ろうとするものが多かった。今、彼らの力量が清朝軍を遥かに上回るから、彼らと手を携えることで北京を危機に陥れることができる。革命にとって、これ以上の好機はない。南北が小事に拘らず連携することが、中国4億同胞にとっての幸というものだ」と。《QED》