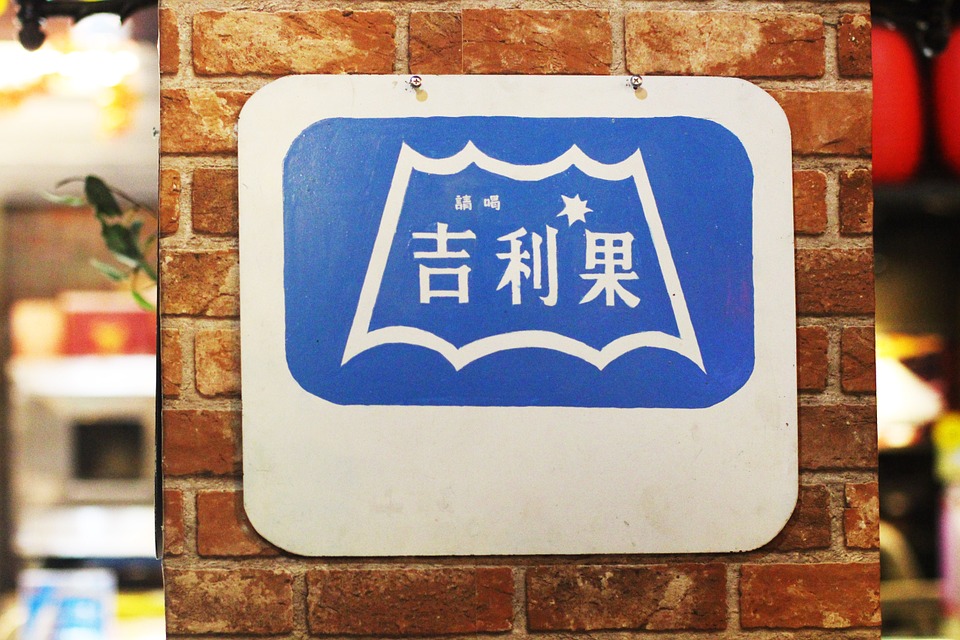――「支那の國ほど近付いてあらの見ゆる國は無し」――關(6)
關和知『西隣游記』(非売品 日清印刷 大正七年)
満洲の炭鉱に関して驚異的な発展を認めているが、経営という視点から考えるなら「滿鐵の支配下に在るは實際大なる不便あり」。それというのも「滿鐵の經濟は直接大藏省に關係を有するが故に、炭礦の施設計畫往々に拘束せらるゝを免れず」。だから炭鉱独自の「擴張發展を爲さんには」、やはり満鉄、ということは大蔵省から切り離して、「炭礦を以て獨立の經營に委」なるしかない。
「滿鐵王國の經營に就いてはその專制的、獨占的、集注的傾向を或程度に制限調節する」必要がある。すでに創業の時を遥かに過ぎたのだから「一切の事業を滿鐵の手に占斷する」のではなく、「寧ろ之を分離、獨營せしむるを適當なりとせずや」。やはり満州を満鉄の天下にしてしまうことは問題なのだ。
だが一たび満鉄の利権を手中にした大蔵省の立場に立てば、満鉄は断固として一括して傘下に置かなければならない。なによりも省益のためだ。かくして満洲経営という国益よりは、満鉄経営という省益が優先されてしまう。なんのことはない、平成という時代が幕を閉じようとしている現在とさほど違いのない構図ということになる。これをいいかえるなら満鉄経営は国家のためであったはずが、省益のため。ということは、どうやら満鉄経営の実態は単なる“お役所仕事”だったと見做されても致し方ない状況だったわけだ。情けないとしかいいようのないほどに情けない話ではある。
「建築、道路、風俗、生活、言語悉く日、露、支三國の特色を代表」する「北滿の咽喉」である長春は、また「歐亞幹線の聯絡點であ」り、「左に蒙古を控へ、右に吉利を擁す、敬称の利、既に未來の大都たるべき使命を有す」。周辺鉄道を建設・整備すれば、「日本と東歐との交通の便は、直に日本海の連絡によりて、大に其の距離を短縮すべし」。「滿、蒙、若くは東歐に對する交通上、長春は實は唯一絶好の地」なのである。
シベリアのチタを起点に満州里から北満を貫き、ハルピンを経てウラジオストックまでを結ぶ中東鉄道に対抗し、日本独自の形で日本海から欧州を結ぼうというのだから、気宇壮大。今風に表現すると“一帯一路”の日本版ということになるだろうか。やがて満洲を舞台に、日露支の3国に加え、米英などが加わって鉄道を巡る虚々実々の駆け引きが始まるのだが、その問題はいずれ詳細に論ずるしかなさそうだ。
奉天に向かうために長春駅へ。ここで「コスモポリタニツク」な風景に出くわす。
「停車場の雜沓甚しく三等客車、滿載の状あり、然して其多數は悉く農民にして、折柄収穫を終りて故郷山東に歸還するものなり、元來此方面の土地は殆ど山東省若くは遼東の農民によりて開墾せられたるものに屬し、春季雪の解くるに及び山東より移り來りて耕作に從ひ、冬季に及びては其穀を賣り金を携へて再び故郷に還る」。つまり彼らは「妻子弟兄家を擧げて」満洲にやってきて働き、収穫が終わって金を手にしたら故郷に戻る。故郷を遥かに離れた満洲という土地であれ、働く場所があるなら出掛ける。まさに「千里北隣の如き彼等の生活其の由來も亦眞にコスモポリタニツクなりと謂うふ可し」である。
そういえばパール・バックの『大地』に、こんな場面があったことを思い出した。
飢饉で生きるすべを失った村人に村の長老が声を掛ける。「『この村を出よう』彼は大きな声で言った。『南へ行くだ!この広い国だで、どこも飢饉だというわけはねえだ。どんなに天が意地悪でも、まさか漢民族をみな殺しにすることもあるめえて』」(大久保康雄訳『大地』河出書房 昭和35年)
關の説く山東や遼東の農民も「どんなに天が意地悪でも、まさか漢民族をみな殺しにすることもあるめえて」との思いを持ち、「コスモポリタニツク」に生きていたはずだ。《QED》