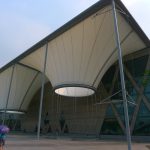――習近平少年の読書遍歴・・・“あの世代”を育てた書籍(習177)
ソロバン(『怎様打算盤』)と健康体操(『初級刀術』)の後はボールペン習字(『鋼筆行書字帖 3』上海書画社)となる。なんとも長閑で拍子抜けするばかり。
毛沢東を讃え、共産党による指導の正しさを賛美し、犠牲を恐れずに敵と戦うことの尊さを唱いあげる革命現代京劇の歌詞が手本として示されている。手本を見ながら歌詞を口ずさみながら手にしたボールペンを走らせる。目と手と口と耳とを動かしながらの革命学習である。ならば学習効果はバツグンだろうが、はたして左程の学習効果は期待できそうにないのだが。
『新兵之歌』(王群生 人民文学出版社)は新兵の趙向陽がマルクス・レーニン主義、そして毛沢東思想に育てられながら、封建社会で先人が嘗めざるを得なかった苦闘の跡を学び、復仇を誓い、革命戦士たちの苦闘の跡を学び、人民解放軍において鋼のような革命戦士に成長するまでを唱いあげる全26章に及ぶ長編詩である。
「第一章 入隊」から「第二六章 革命のために永遠に戦う」まで、「共産党員のマナコは永遠に前を向く」「前を見よ!共産主義の輝かしい光りだ」「前へ! 前へ! 前へ! 毛主席は風を御し、中国革命の巨船を前に進める。共産主義に向かって前進だ! 歴史の歩みは誰にも止められない・・・」「毛主席の革命路線を推し進める戦士は永遠に前線に立つ・・・」など文革ではお馴染みの“常套句”がテンコモリである。
初版出版は文革開始1年前の1965年3月だが、内容からして文革を想定していたようにも思える。それにしても主人公の名前が趙向陽――陽(=毛沢東)に向かう・靡く・慕う――とは、なんとも予定調和が過ぎてウソ臭い。だから面白い。
『軍墾新曲』(旭宇 火華等 人民出版社)は内蒙古、蘭州、黒龍江、浙江、新疆などに下放され各地の生産建設部隊に参加した都市青年たちの詩集である。
「開墾戦士、毛主席に見える」「党の恩情は永遠に忘れない」「開墾戦士は党に忠誠を誓う」「永遠に毛主席に付き随う」「毛主席は幸せの水をお運びになる」などの題を並べてみるだけでも、なにを謳い上げようとする詩であるかは容易に想像できるだろう。率直に言って毛沢東と党に対するどうでもいいオベンチャラの羅列だが、だからといって詩としてツマラナイなどと批判しても始まらない。だから、オベンチャラが詩として持て囃された当時の時代環境を確認しておくだけで十分だろう。
『李時珍与《本草綱目》』(鐘毅 上海人民出版社)は、薬草を含め薬になる天然自然の産物を研究する学問を最初に集大成した李時珍(1518~93年)の生涯を、その研究人生に沿って綴っている。
文革に李時珍とは不思議な取り合わせとは思うだろうが、李時珍の苦闘の生涯を「人の正しい思想は社会における実践に加え、社会における生産闘争・階級闘争・科学実験の3つの実践からしか生み出せない」との毛沢東の教えに沿って描き出すことで、政敵の劉少奇を唯心主義者として批判・断罪しようというのだ。
だがマトモに考えて、李時珍を使った劉少奇批判に何ほどの説得力がるというのか。限りなく皆無に近いと思うのだが、有ると考える、有ると信じ込んでいる、あるいは有ると信じている風を装っているところに文革時の、いや文革と呼ばれる極めて特殊な時期に限らない中国人の思考パターンのカラクリの一端が隠れているに違いない。
李時珍の個人的能力、明代という時代、当時の社会環境から考えるならやむを得ないことだが、『本草綱目』には誤った記述やら珍妙な見解も見られる。『李時珍与《本草綱目》』は、その業績からして李時珍は「永遠に人々の記憶に留めるべき」だが、やはり過ちは正さなければならない、と説く。だが、その誤った記述やら珍妙な見解が面白い。《QED》